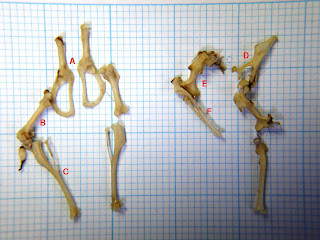昨日、久しぶりに土山峠から堤川林道の終点までいき、そこから宮ヶ瀬尾根に
登り、不思議なミズキ・熊ノ爪・祠の峠・辺室山・土山峠と歩いてきた。
始めの目的は鍋嵐だった。
が、久しぶりの丹沢なので、出かける準備に整わず出かけるのを止めようかなと思ったが、
9時に家を出ることができた。
案の定の朝の渋滞で、裏通りのショートカットの道を選んで清川村に向かった。
土山峠には10時半に着いた。1時間半で着いたのだから裏道を通ったのが正解だ。
土山峠に車を置いて、柵を乗り越えると、もう雪だ。
が、そんな氷雪の中にカエルが卵を産んでいる。ということではなくて、今年ももしかしたらヤマアカガエルがわずかな水溜まりに卵を産んでいないかな?っと注意して側溝を見ながら歩いたのだ。
寒い中、交尾してメスは卵塊を産み出し、また穴の中にでも潜ったのだろうか?
卵は凍っても大丈夫ということなのだろう。
変温動物だからできる芸当だ!
堤川林道は日蔭は凍った雪が残り、陽が当たるところは雪無しだ。
この日は、歩き出しから膝の調子が悪いのでゆっくりゆっくり歩く。
途中の見晴しの良いところで鍋嵐をみる。真ん中の尖ったピークが鍋嵐。
宮ヶ瀬尾根に辿り着いた時は、既に12時を回っている。土山峠から1時間半もかかっている。
今回は、前夜に「丹沢サル観察し隊」の二人を誘ったが、二人とも来られなかったので良かった。
ぼくのノロイ歩きにはイライラしたことだろう。
宮ヶ瀬尾根の堤川林道とハタチガサワ林道の出合となる場所で、
休憩を兼ねてアイゼンと尻皮をつける。
バスの中に学生が置き忘れたこの尻皮は、バス会社(伊勢原営業所)に頼んで着払いで送ってもらったのだ。親切に応対してくれた係りの上原様に感謝!
ここから、「不思議なミズキ」を通過したのが、13時半あった。アイゼンを付けた出合いの場所から1時間半も掛かっている。もう、完全に鍋嵐は諦めた。
腐ったような雪であり、3、40センチ積もったところもあれば、林床が出ているところもある。
13時半、「熊ノ爪」のピークにはそれから15分もかかる。
アイゼンの裏に腐れ雪が固まって付き歩き辛い。
鍋嵐の方へ下りてみる。鍋嵐に向かう北側の斜面は全て雪で覆われている。
14時4分辺室山・物見峠の登山路がある「祠の峠」にでる。ここは雪無しだ。
まだ、お昼用に持ってきたインスタントラーメンを食べてないので、ここでお湯を沸かして食べようかなとも思ったが、もう14時を回っているので、コンビニで買った餡ドウナツだけを食べ、写真を撮って出発だ。
さすが、登山道だ。登山靴の足跡がたくさんある。
登山道を歩いていたら、登山者の足跡に消されて動物たちの足跡や他の痕跡は見つけるのが難しいのだ。
辺室山山頂には14時50分に着く。
下りは膝痛との戦いのようでもあり、一歩一歩ゆっくり足を下ろして進む。
土山峠の登山口に辿り着いたのは17時丁度であった。
日が長くなってきているので助かった。
アイゼンやスパッツ、尻皮をはずし、車に乗り込む。
この日のGPS上のルートである。
先日の学生との大山登山の帰路ですっかり膝を痛めたようだ。
痛みが治まるまでしばらく丹沢はお休みにしよう。












.jpg)